【令和7年度対応】処遇改善等加算の「一本化」で保育経営はどう変わる? ~今、園長・経営者が備えるべき実務対応とは~
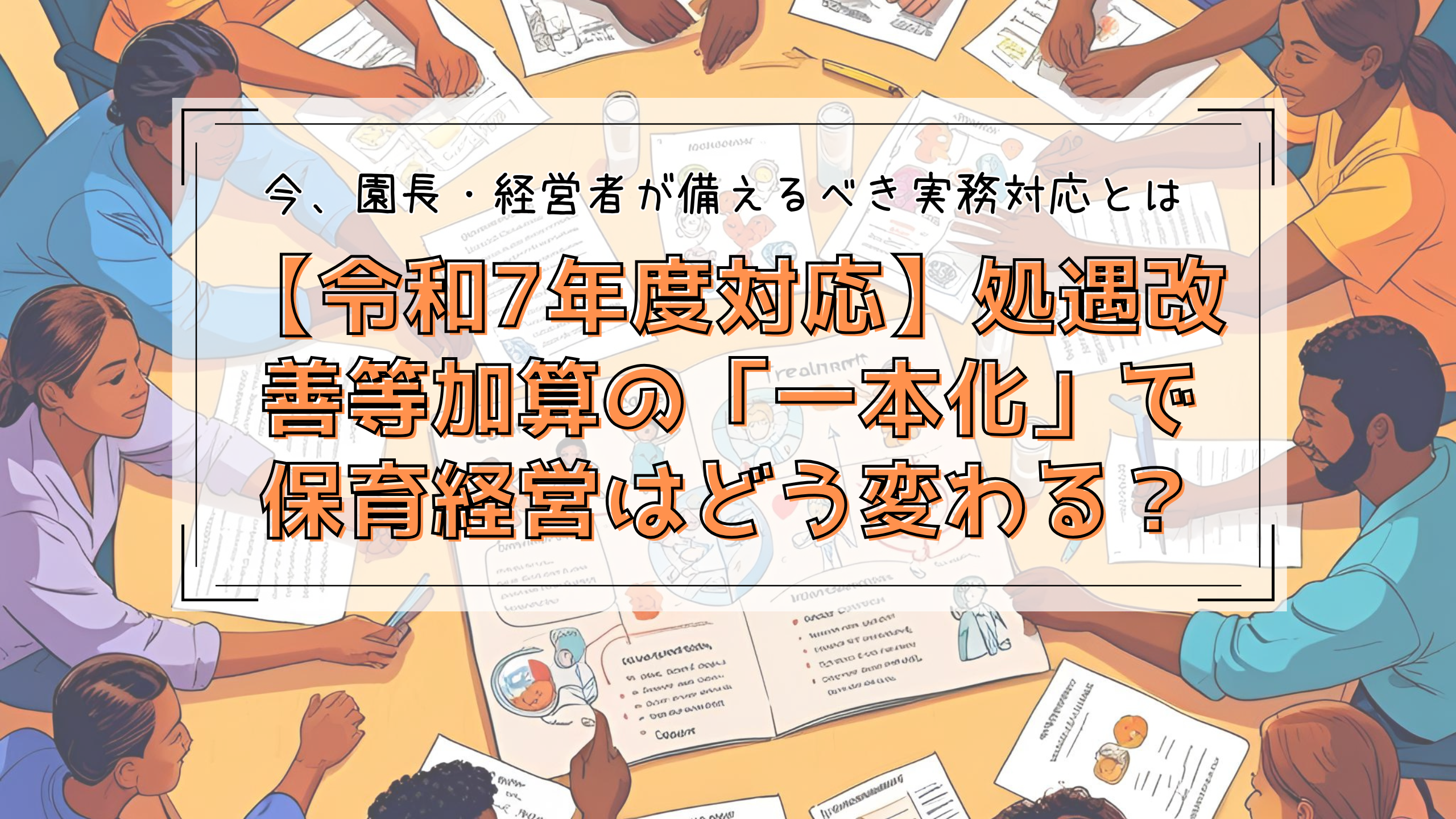
目次
1. はじめに
2025年度(令和7年度)から、保育事業における「処遇改善等加算」が大幅に改正され、従来の複雑な加算制度が一本化されることが決定しました。
これまでの処遇改善等加算は、加算Ⅰ、加算Ⅱ、加算Ⅲと複数の種類が存在し、それぞれ支給対象、要件、配分方法が異なっていたため、現場ではその運用に多くの労力と専門知識が求められていました。
これまで存在していた加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの区分が廃止され、処遇改善等加算として一元的に整理されることになりました。その結果、名称や配分ルール、要件も明確化されています。
この制度変更は、単に加算の仕組みが変わるだけでなく、今後の保育経営において「人事制度の戦略的な見直し」「職員への丁寧な説明と理解促進」「経営状況の透明性の確保(見える化)」が、これまで以上に重要となることを示唆しています。
本コラムでは、保育事業者の経営者や園長先生方が、この大きな変化に適切に対応できるよう、新制度の具体的な概要と、今から着手すべき実務対応について、分かりやすく解説いたします。
2. 処遇改善等加算の「一本化」とは? 3つの区分とそのポイント
一本化後の処遇改善等加算は、その目的と内容に応じて以下の3つの区分に整理されます。この区分を理解することが、新制度への対応の第一歩となります。
- 区分①(基礎分):
・目的: 職員の経験に応じた昇給の仕組みを整備し、職場環境全体の改善を促進することを目的とします。
・主なポイント: この区分を受け取るためには、施設が国の定める「キャリアパス要件」を確実に満たしていることが必須となります。キャリアパス要件とは、職員の職位、職務内容、能力に応じた明確な昇進・昇給の仕組みを設けることを指します。 - 区分②(賃金改善分):
・目的: 職員の賃金改善を直接的に図り、特に経験年数に応じた賃金の上昇を促します。
・主なポイント: 従来の加算Ⅰ(賃金改善要件分)と加算Ⅲがこの区分に統合されます。支給方法は、区分2と区分3の合計額の1/2以上を基本給や毎月支給される手当として支給する必要があり、残額については一時金として支給することが可能です。
- 区分③(質の向上分):
・目的: 職員の専門的な技能や経験の向上、特にキャリアアップ研修の受講を奨励し、その成果に応じた追加的な賃金改善を行うことを目的とします。
・主なポイント: この加算額は、毎年4月1日時点でのキャリアアップ研修修了者数に基づいて決定されます。計画的な研修受講を促し、職員の専門性向上を経営戦略に組み込むことが、加算額の最大化につながります。
| 区分 | 目的 | 主なポイント |
| 区分①(基礎分) | 職員の経験に応じた昇給の仕組みを整備し、職場環境全体の改善を促進する | ・国が定める「キャリアパス要件」の充足が必須・職位・職務・能力に応じた昇進・昇給制度の整備が求められる |
| 区分②(賃金改善分) | 職員の賃金改善を直接的に図り、特に経験年数に応じた賃金上昇を促進する | ・従来の加算Ⅰ(賃金改善要件分)と加算Ⅲを統合・区分2と区分3の合計額の1/2以上を、基本給や毎月支払われる手当で改善し、残額は一時金での支給も可 |
| 区分③(質の向上分) | キャリアアップ研修の受講を促し、成果に応じた追加的な賃金改善を行う | ・4月1日時点の研修修了者数に基づいて加算額が決定・計画的な研修受講が加算額の最大化に直結する |
これらの区分の中でも特に注目すべきは、キャリアパス要件を満たさない場合、区分①(基礎分)が不支給となるという点です。
これは、単に賃金を上げるだけでなく、職員のキャリア形成を支援する仕組みの整備が、加算を受ける上で不可欠であることを明確に示しています。
また、区分③の加算額が4月1日時点の研修修了者数に依存することから、年度当初に向けた計画的な研修実施が、これまで以上に重要になります。
見落とし厳禁!対応が遅れると加算が受けられないリスクも!
| ⚠️ 注意ポイント | 何に注意すべきか | 対応が遅れるとどうなる? | 優先すべき対応策 |
| 区分①(基礎分) | キャリアパス要件の整備 | 要件を満たしていない場合、「令和8年度以降は区分①(基礎分)がまるごと不支給となる」ため、令和7年度中の整備が急務 | 職位・職務・能力に応じた昇給・昇格制度を明文化し、就業規則へ反映 |
| 区分③(質の向上分) | 研修修了者の把握と計画 | 4月1日時点での修了者数が少ないと加算額が減額される | 年度末までに修了見込みの職員を把握し、計画的な研修実施スケジュールを策定 |
3.処遇改善等加算一本化に伴う主な変更点と留意事項
新制度へのスムーズな移行のためには、具体的な変更点を正確に理解し、準備を進める必要があります。
1. キャリアパス要件の厳格化と重要性
旧制度では、加算Ⅰの賃金改善要件分(加算率6~7%)において、キャリアパス要件を満たさない場合に2%の減額措置が講じられていました。しかし、一本化後は、区分①(基礎分)の必須要件となり、これを満たさなければ基礎分自体が支給されなくなります。これは、施設として職員のキャリア形成に対する責任をより強く問われることを意味します。
ただし、令和7年度に限り、既存のルールが適用され、区分②から減額される仕組みが継続される見込みです。この猶予期間を有効活用し、キャリアパス要件の整備を進めることが賢明です。
【特に注意】令和7年度は「最後の猶予」!キャリアパス未整備だと支給ゼロに?
| 年度 | 要件未達成時の影響 | 適用されるルール | 経営者・園長がすべきこと |
| 令和7年度 | 基礎分は支給、区分②から一部減額で対応 | 現行ルールの経過措置が継続(減額対応) | 猶予期間のうちにキャリアパス要件を整備!※制度設計+就業規則反映が必要 |
| 令和8年度以降 | 区分①(基礎分)がまるごと不支給になる | 新制度が完全適用(要件未達=支給停止) | 未対応だと職員の昇給財源が消滅→制度未整備は経営リスクに直結! |
2. 配分ルールの統一による柔軟性の向上
これまでは、加算の種類ごとに支給方法(月額か一時金か)に細かなルールが存在し、運用の複雑さの一因となっていました。
一本化後は、区分②と区分③の合計額の2分の1以上を基本給や毎月支払われる手当として支給し、残りの金額は一時金(賞与等)で支給することが可能となります。この配分ルールは制度要件を前提としたうえで、経営状況や職員ニーズに合わせた柔軟な実務設計を行う余地を与えるものです。
【制度改正のチャンス】配分ルールが柔軟に!今こそ「月額」と「賞与」の最適設計を
| 項目 | 改正前(旧制度) | 改正後(一本化後) | 意味すること |
| 支給方法 | 加算種別ごとに月額・一時金の制限あり | 制度要件として区分②+③の合計額の1/2以上を基本給や月額手当として支給する必要があり、残りは一時金も可 | 園ごとに柔軟な設計が可能に |
| 配分の自由度 | 制限が多く、対応が煩雑 | 経営判断で割合を選べる | 人件費管理・職員満足度の両立が可能に!※なお、新制度では、リーダーに相当する職位や職務命令があれば、研修修了前でも加算対象となる柔軟な運用が可能に。ただし、要件は引き続き必要。 |
| 配分戦略を怠ると… | 旧制度に倣いすぎて柔軟性を活かせない | 制度上は自由でも、実務設計をしないと損をする! | 配分の「設計不足」は制度活用の失敗を招く |
※一本化後は「加算対象者」の認定基準も見直され、リーダー相当の職位や職務命令を受けている職員であれば、研修修了前であっても対象となる場合があります。
ただし、あくまでリーダー的役割が明確な職員に限定されており、誰でも対象になるわけではない点には注意が必要です。
3. 「賃金改善」の認定基準の見直し
旧制度では、処遇改善等加算を算定する際の「起点賃金水準」(基本給等に処遇改善等加算や前年度までの人勧分を含めた金額)を下回らないことが賃金改善の要件とされていました。
しかし、一本化後は、加算当年度において、算出された加算額以上の改善額となっていれば、賃金改善を行ったと認められるようになります。
これは、例えば園児数の減少により加算額が前年より減額になった場合でも、その年度に算出された加算額を全額職員に配分していれば、要件を満たすという解釈が可能になったことを意味します。
ただし、これは職員の賃金を引き下げても良いという意図ではありません。既存の労働契約法における「不利益変更」の原則は依然として適用されるため、賃金を下げる場合には、労働者との丁寧な話し合いと合意形成が不可欠です。
賃金改善要件の見直し:柔軟になったけど“賃下げOK”ではない!
| 項目 | 改正前(旧制度) | 改正後(一本化後) | 誤解しがちなリスク | 正しい対応 |
| 賃金改善の要件 | 起点賃金水準(前年)を下回らないこと | 当年度の加算額以上を職員に配分していればOK | ただしこれは、「前年より少なくてよい=賃下げしてもよい」という意味ではなく、職員との合意形成を前提とした不利益変更の手続きが必要 | 加算額減でも支給根拠の丁寧な説明と合意が必須 |
| 園児数減少などで加算が減額された場合 | 前年水準を維持する必要あり | 当年加算額内で支給すれば改善扱い | 財源不足を理由に一方的な減額を実施 | 合理的な理由、労使の合意の上、不利益変更する |
| 柔軟性の意味 | 経営の裁量が小さい | 加算額に応じた運用が可能 | 労働契約の原則まで変更されたと誤解 | 法的制約(労働契約法)を順守することが前提 |
4. キャリアアップ研修の評価基準の変更
旧制度では、必要なキャリアアップ研修の分野数を修了した職員は、修了した翌月から加算Ⅱの対象となっていました。一本化後は、毎年4月1日時点での研修修了者数に基づいて施設全体の加算額が決定されることになります。
この変更により、年度当初に加算額を確定させるため、研修計画を早期に策定し、年度末までに修了見込みの職員を把握しておくことがより重要になります。
なお、研修修了予定者であっても、リーダーに相当する職位の発令や職務命令を受けていれば加算対象職員とすることができます。
キャリアアップ研修の評価基準が変更!計画的な受講が加算額に直結
| 項目 | 改正前(旧制度) | 改正後(一本化後) | 留意点 | 今、やるべきこと |
| 加算の基準時点 | 研修修了の翌月から加算Ⅱ対象 | 4月1日時点の修了者数に基づき施設単位で加算額を決定 | 研修が年度末にずれ込むと加算に反映されない | 年度末までに修了予定者の進捗を確実に把握・管理 |
| 加算対象の単位 | 個人単位(対象者が個別に加算) | 施設単位(全体の修了者数で加算額が変動) | 施設全体で研修進捗管理が必要不可欠 | 法人として計画的に研修受講を設計・推進する体制を構築 |
| 研修修了予定者の扱い | 原則、修了後に適用 | リーダー職など職務命令があれば加算対象に含める可 | 育成と配置の整合性が求められる | 職位・配置と連動した育成設計を強化する |
4. 実務で何を準備すべきか? 園長・法人がやるべき具体的な対応
今回の制度改正を機に、貴園の運営体制を見直し、より強固なものとするための具体的なステップを以下に示します。
1. 賃金制度・就業規則の徹底的な見直しと明確化
処遇改善等加算は職員の賃金の一部として扱われるため、その支給に関する明確なルールを就業規則に盛り込むことが不可欠です。具体的には、以下の項目について記載の有無を確認し、必要に応じて改訂しましょう。
・支給要件: どのような職員が加算の対象となるのか。
・支給方法: 基本給、月額手当、賞与など、どのように支給されるのか。
・月額手当の名称: 加算として支給する手当に具体的な名称を付与する。
・金額の決定基準: どのように金額が決定されるのか(例:経験年数、役職、評価など)。
・昇給の種類: 定期昇給、ベースアップ、昇格昇給など、昇給の仕組みを明確にする。 就業規則の改訂後は、職員への丁寧な説明会を実施し、疑問点を解消する場を設けることで、透明性を確保し、職員の納得感を高めることができます。
2. 支給方法と配分バランスの見直し(賞与・月額の設計)
処遇改善等加算の一本化に伴い、区分②・区分③に対応する支給方法が統一されました。これにより、施設ごとに「月額支給と賞与支給のバランス」が改めて問われるようになっています。
具体的には、「区分②と③の合計額の1/2以上」を、基本給や毎月決まって支払われる手当として月額で支給することが求められるようになりました。これは制度要件として定められているため、まずは自園の現状の支給方法がこの基準を満たしているかどうかを確認することが重要です。
ただし、すべての施設が大きく制度変更を求められるわけではありません。もともと月額中心で支給しており、制度要件を満たしている場合には、現状のままで問題ないケースも多くあります。逆に、配分のバランスに偏りがある場合は、微調整により要件を満たせる可能性があります。
たとえば、賞与に多くを振り分けていた場合には、
・「月額手当に一部を移行する」
・「一時金の一部を定額手当として分割支給する」
といった柔軟な対応が可能です。これは、職員の生活への影響を最小限に抑える配慮であり、施設側・職員側双方の混乱を避けるための工夫と言えます。
今後は、制度要件に適合させつつ、各施設の実情に応じた実践的な運用設計が求められます。「一律に変更する」ではなく、「無理のない方法で、自園に合った支給設計を見直す」姿勢が大切です。
3. 人事評価制度の積極的な活用と賃金体系の整備
今回の処遇改善等加算の一本化において、最も戦略的に活用すべきは「人事評価制度」です。
これまでは年功序列型の賃金体系が採用されやすい傾向にありましたが、今後は人事評価をもとにした昇給の根拠や、処遇改善の位置づけを明確に整理することが求められます。
具体的な対応としては、成果基準の明確化(経験年数、役職、能力評価、職務遂行能力、積極性など)を通じて、職員への丁寧な説明と理解を促す必要があります。
園児減少による加算額の減額リスクがある中でも、高い貢献度を持つ職員の賃金水準を維持・向上させるためには、公正かつ透明性のある人事評価制度が不可欠です。これにより、職員は自身の努力や貢献が正当に評価され、賃金に反映されることを実感でき、モチベーションの向上にもつながります。
4. 経営情報の継続的な見える化への対応と戦略的な活用
令和7年度からは、子ども・子育て支援制度において、各施設の「継続的な見える化」の公表項目が拡大されます。具体的には、施設ごとに以下の3項目が追加で公表されることになります。
- ①モデル給与: 保育士等の常勤職員について、経験年数、役職ごとの基本給、各種手当、賞与、月収、年収の目安を具体的に明示することが必須となります。
- ②人件費比率: 施設運営における人件費がどの程度の割合を占めているかを示します。
- ③職員配置状況: 職員の配置人数や体制などが示されます。
これらの情報は、幼児教育・保育を取り巻く現状への国民の理解を深めるとともに、保護者や保育士を目指す求職者が施設を選ぶ際の重要な判断材料となります。
さらに、以下の項目は任意記載となりますが、積極的に開示することで、貴園の魅力や強みを社会に発信する絶好の機会となります。
・給与決定方法、賞与支給基準、時間外手当・退職手当の取扱い
・福利厚生の内容
・その他、職員の処遇に関する事項
・ICTへの取り組み状況
・平均有給休暇消化率、離職率
・人材育成に向けた取り組み(研修制度の充実度など)
これらの情報を丁寧に開示することは、単なる義務履行にとどまらず、貴園が「職員を大切にする法人」であることを内外に示すブランディング(経営)戦略の一環となります。特に、就職活動中の保育学生や現職の保育士にとっては、貴園の職場環境やキャリアパスの魅力を具体的に伝える強力なツールとなっていきます。
5. まとめ
今回の処遇改善等加算の一本化は、単なる制度改正ではなく、保育事業者が持続可能な経営を実現するための重要な契機となります。変化を正しく理解し、先んじて対応することで、貴園の競争力を高めることができます。
特に、職員の皆様が処遇改善等加算の仕組みや、それを通じた法人の賃金決定方針を深く理解することは、園と職員間の信頼関係を構築し、待遇に対する納得感を醸成する上で不可欠です。この信頼関係が、職員の定着率向上やモチベーション維持に直結します。
また、経営情報の継続的な見える化は、貴園が職員を大切にし、質の高い保育を提供していることを社会に積極的にアピールする強力な手段となります。必須項目だけでなく、任意項目も最大限に活用し、貴園の理念や働きやすさを明確に示していくことが、これからの少子化社会において、優秀な人材の確保と安定した園運営を実現するための不可欠な経営戦略となるでしょう。
最新のセミナー情報はこちら
執筆者プロフィール

カタグルマ事務局
株式会社カタグルマ
監修:株式会社カタグルマ 代表取締役/CEO 大嶽広展











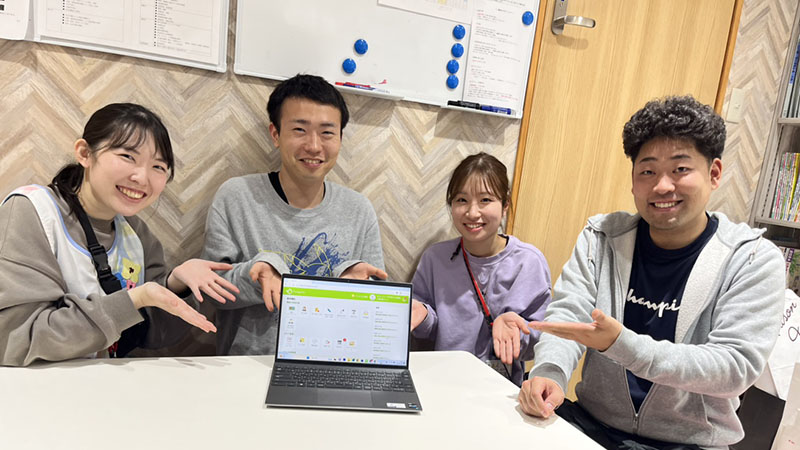
城南学戦様.jpg)





