保育園内の”サイロ化”に気をつけろ!
コミュニケーション活性化で分業を解消
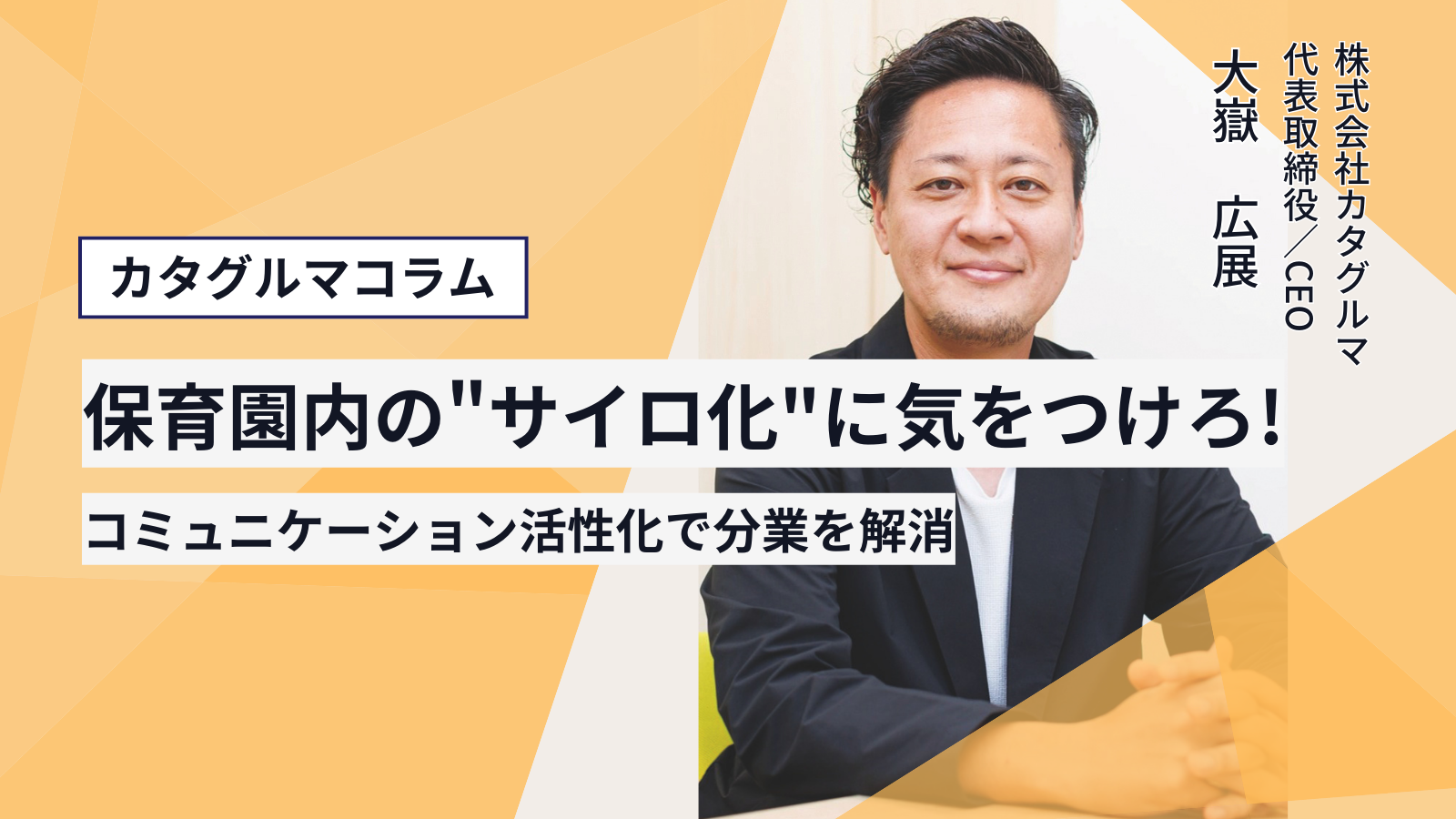
保育園内の分業化と縦割り構造
みなさん、いつもご愛読いただきまして誠にありがとうございます。
カタグルマ代表の大嶽と申します。
今回は、
「保育施設内の分業化と縦割り構造が招くリスクと対策」
をテーマとし、お伝えしたいと思います。
保育施設の中でも特に保育園や認定こども園においては、
・担当クラスという分業
・調理、事務、看護(保健)という分業
によって組織が構成されているのは言うまでもありません。
当たり前のように、一つの組織内で担当が分かれ、それぞれで分業化している状態です。
この分業化というのはメリットもあればデメリットもあります。
◆メリット
・専門性が向上する
・業務や担当が明確になる
・管理がしやすくなる
◆デメリット
・コミュニケーションの断絶が起こりやすい
・ブラックボックス(その担当にしか分からないこと)が生まれやすい・全体視点が欠けやすい(自信の持ち場さえ良ければよい等)
保育に関しては、仮に担当クラスが異なったとしても、
・同じ保育業務を行っていること
・発達の連続性などの理由から情報共有すべき機会が多いこと
・園によっては異年齢保育や縦割り保育によって他クラスの子ども達や保育、業務に関しての情報共有しやすい環境があること
などデメリットが補われる環境も一部あります。
では、調理現場はどうでしょうか?
・給食会議や調理会議を月に1回(もしくは2回程度)実施している
・何かあったときに栄養士や調理員が声をかけてくれるので相談体制は整っている
・食育活動等で保育士との交流もあり、コミュニケーションは取れている
という環境の中で、コミュニケーション、情報共有、人間関係、業務進捗等に問題はないと捉えている園長先生やリーダーの先生も少なくないかもしれません。
保育と給食の”サイロ化”リスク
私が以前、ある保育施設の業務改善や保育の可視化、研修体系の構築、社内情報共有体制の整備などの運営支援を行っていた際に、園長と給食現場の調理員から以下のような声をいただいたことがあります。
<園長>
「調理のことは専門外だし、任せるしかないかな・・・給食会議には出来るだけ参加したり、栄養士さんや調理員さんの要望は聞くようにしよう・・・
給食現場も大変そうだし、あまり仕事を与えるのも気が引ける。。」
<調理員>
「給食の仕事は大変だけど、保育も大変そうだし、園長先生も忙しいからあまり相談しにくい・・・会議などでコミュニケーションは取るけど、普段はほとんど無く、何だか給食室だけ孤立している・・私たちももっと子どもと関わる場が欲しいのに・・」
分業体制が故に、お互いの専門性を尊重しすぎるあまり、会議などの形式的なコミュニケーションは取れているものの、より深いところでの相談や議論が出来ておらず、特に給食現場の職員からは不安や不満因子になっていたということです。
このような状況は円滑で問題ないと思われている園も、多かれ少なかれ潜在的に潜んでおります。
そして、これは一般的なマネジメント論としては、「分業化」という仕組みがもたらす典型的な状態でもあり、この状態を「サイロ化現象」と呼びます。
サイロ化とは、
「仕事が個別化してしまい、身近で働く人がどのような業務を行なっているかわからない状態」
と定義されます。
そして、このサイロ化は仕組みをつくり、日々対策を打ち続けないと、様々な場面でリスクを生み出すことになります。
今回は保育現場と給食現場の事例を上げましたが、分業化されているケースであればどれも当てはまる可能性がある現象です。
では、どのようにすれば、このようなサイロ化を解消して円滑な組織を築き上げることが出来るのでしょうか?
コミュニケーションと情報共有でサイロ化を解消
これらを解消するためには2つのカギがあります。
それが、
1.コミュニケーションの活性化
2.情報共有の仕組み化・デジタル化
です。
とても抽象的な表現で、ありきたりな表現に思えるかもしれませんが、この2つのカギの詳細について新たなアプローチと事例を交え、特に保育現場と給食現場のサイロ化を解消する方法を以下のリアルセミナーでご紹介したいと思っております。
8/22(木)保育給食カンファレンス2024夏
詳細・お申込みはこちら ※当セミナーは終了いたしました。
最新のセミナー情報はこちら
執筆者プロフィール





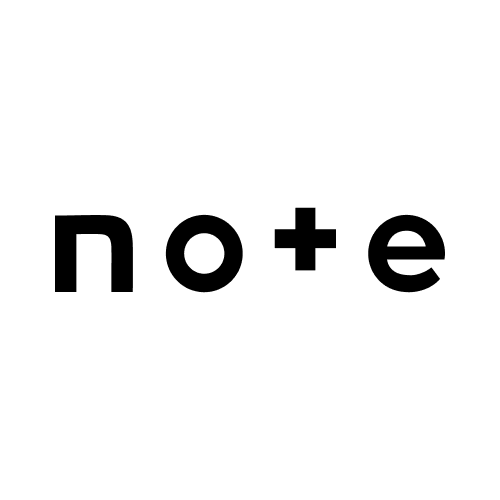





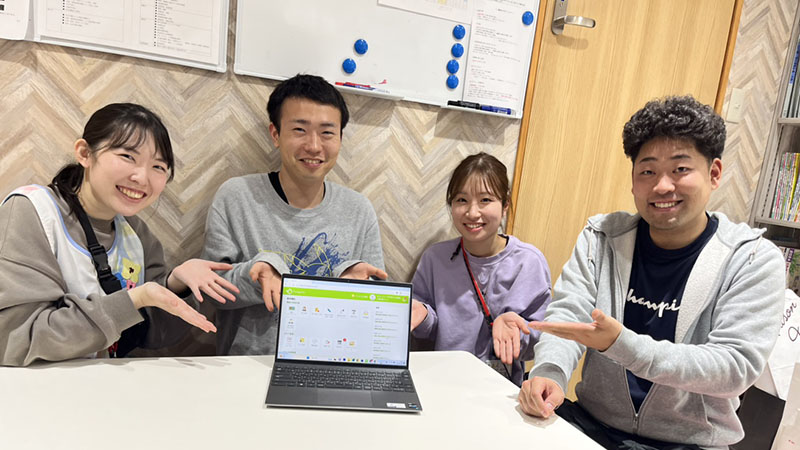
城南学戦様.jpg)





