保育園の経営が厳しい時こそ、大切にすべき処遇改善のポイント
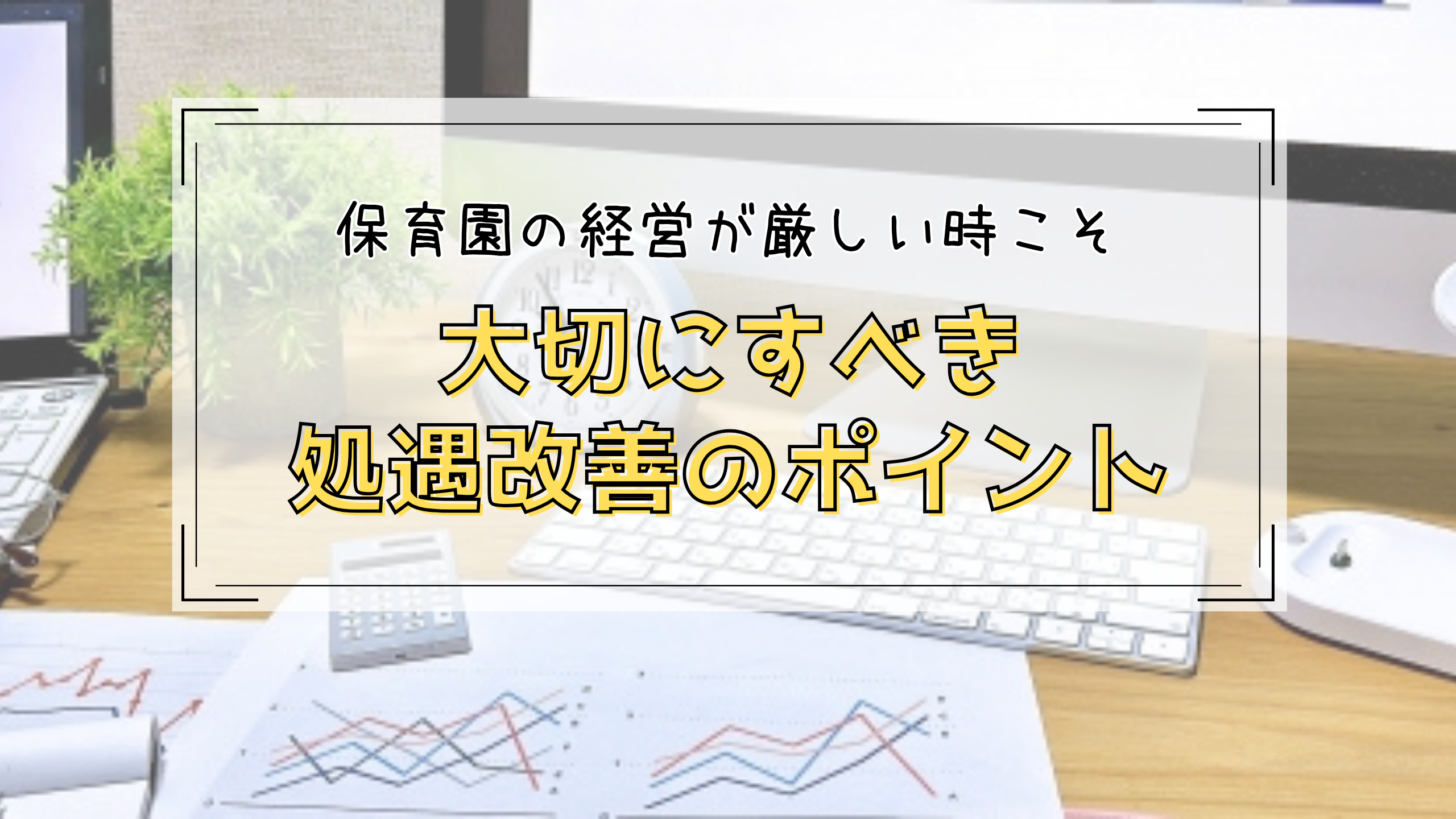
目次
園児数減少は業績低下ではない!処遇改善加算の本来の趣旨とは
園児の人数と施設の収入は密接に結びついていますが、昨今の園児減少の影響を受けて委託費が減少し、賃下げによって人件費を抑えたいというご相談も増えてきました。
業績が悪化して収入も減ってしまったのだからやむを得ないと考えたいところですが、保育所等の場合は注意が必要です。
少子化の影響による園児減少を業績低下と捉えて賃金の引き下げを行うケースが散見されますが、国の処遇改善等加算通知第3の2で示す「業績等」は職員の評価につながる業績のことをいいます。
園児数が減っても職員の処遇は守れ!様々な工夫で収支改善に取り組もう
このため、園児の減少といった事業業績に関することについては、まず法人・施設の努力や制度活用を優先します。
たとえば、
◎業務改善によって残業を削減。これまで支払っていた残業代を月額給与として支払う
◎保育の質をより良くしたり、地域に広く知ってもらいながら園児獲得のために努める
◎定員変更によって基本分単価を引き上げて収支を好転させる
◎一時預かり事業や子育て支援事業実施で機能を充実させる
このように、職員の待遇維持は施設や法人ができる限り堅持すべきものという認識を持ったうえで、それでも難しい場合に職員評価に基づく賃金の適正化を行うという手順が必要です。
賃金改定は慎重に!不利益変更の手順と4つの判断基準
そして就業規則を変えたからすぐに実行できるわけでもなく、労働契約法に基づく不利益変更の適切な手順を踏むことも重要です。
この不利益変更で検討すべき事項としては以下の4つのポイントを見て判断します。
・労働者の受ける不利益の程度
・労働条件の変更の必要性
・変更後の就業規則の内容の相当性
・労働組合等との交渉の状況
これらの基準を見ても事業者一人で判断できるような明確な基準ではないことがお分かりでしょう。
職員の生活がかかっているわけですから事業者と職員と丁寧に話し合いをして書面で同意を得て、さらに急激な変更を避けるために移行期間を設けて・・・と最大限の配慮を要します。
経営と処遇改善のバランスを!評価制度の見直しが将来に備える糸口
だからこそ、経営が苦しいと思ってから対処しても遅いのです。
とはいえ、選ばれる園になるための努力が最も重要であることは紛れのない事実ですが、職員の待遇を維持することだけを考えて園運営が成り立たなくなってしまっては職員にとっても不利益です。
こうしたリスクも見据えて賃金制度のあり方や育成と適正な評価を根本から考えておくことがますます重要になるといえます。
経験年数さえ上がれば自動的に昇給するしくみは安心感がありますが、職員の意欲向上やキャリアアップの意識につながらない場合がありますし、何より少子化・園児減少といった外的要因には非常に厳しいしくみとなり得ます。
数年スパンで徐々に改革し、職員が自己目標を持ちながら評価と振り返りを行い、自分の処遇・待遇に納得感を持てるようにしていくことも考えていく必要があるのではないでしょうか。
社会保険労務士法人ワーク・イノベーションのHPはこちらより
最新のセミナー情報はこちら
執筆者プロフィール











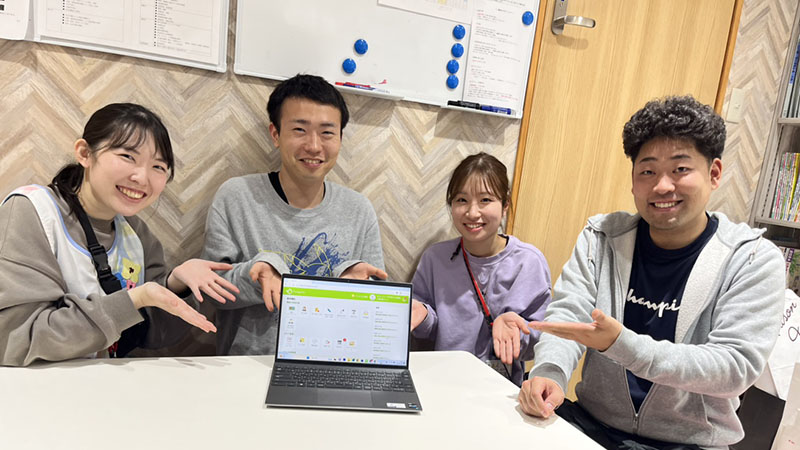
城南学戦様.jpg)





