保育園の人材不足解消に向けて。RJP理論で定着促進を
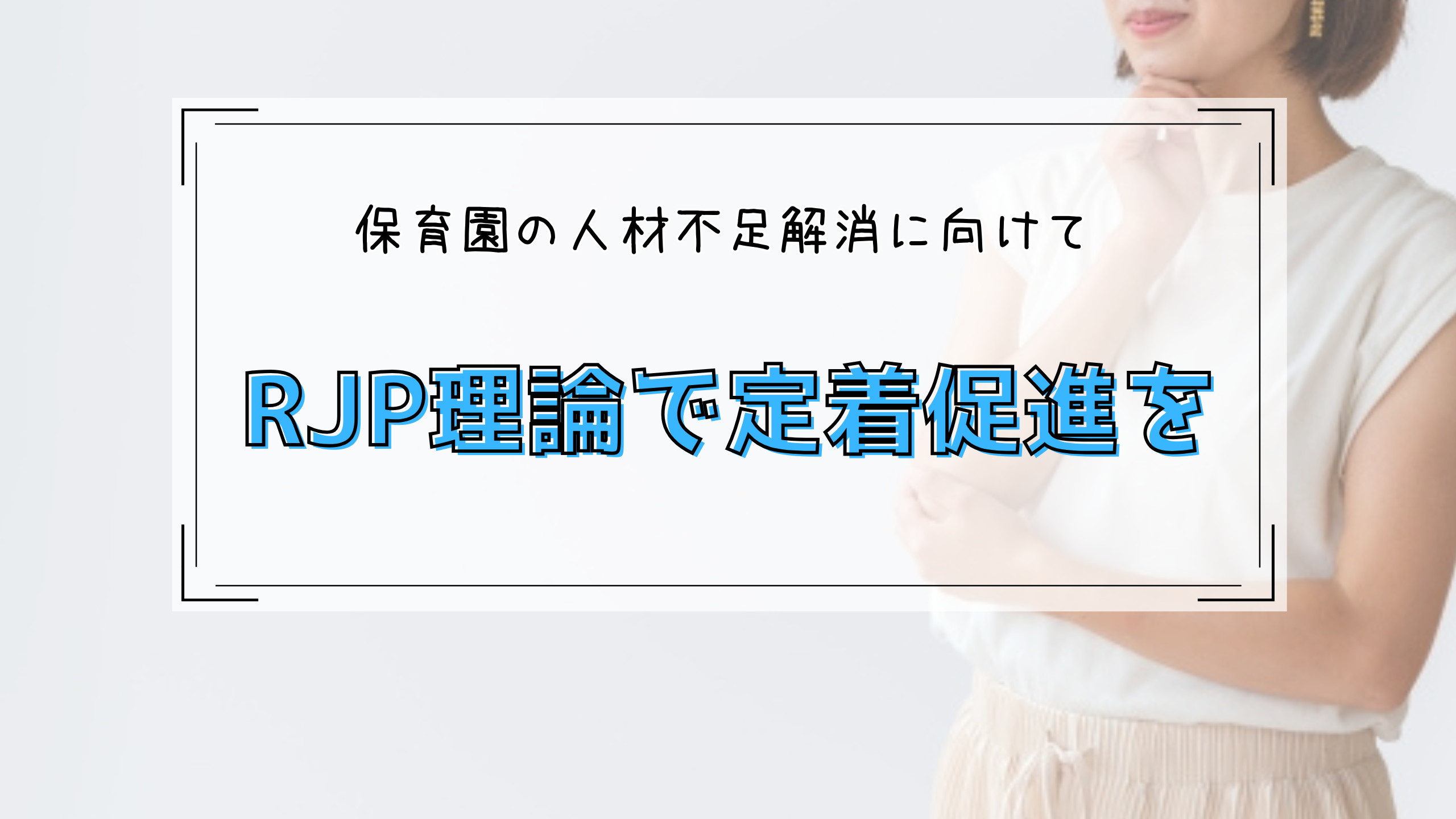
保育業界の人材確保が一層深刻に
こんにちは!カタグルマの八巻(やまき)と申します。
いつもカタグルマNEWSを読んでいただき、ありがとうございます。
少し前になりますが、今年度の「私立大学・短期大学等 入学志願動向(日本私立学校振興・共済事業団)」が公開されました。
内容を見ると私立大学は53%、私立短大は92%の学校が定員割れ。
教育・家政系の学部学科も軒並み定員充足率が低下し、特に短期大学の定員割れは深刻化。
・今後も新卒不足が加速(業界問わず)
・保育の新卒競争もさらに激化
・保育学生の四大生比率が高まる
…短大・専門に頼った採用が厳しく
…他業界との取り合いが激しく
影響は中途採用にも…などなど…が予想される内容でした。
人材の質の低下も危惧される
また、採用で売り手市場となるにつれ加速するのが、人材の質の低下。
その点も踏まえると今後の保育・教育・療育業界では(でも)
採用・定着・育成
が、これまで以上に重要になりそうです。
実際に、厳しい環境の中、業界問わず「定着・育成」の重視傾向が続いています。
定着促進に注目されるRJP理論
そこで今日は、早期離職の防止策として改めて注目されている「RJP理論」をご紹介します!
RJP(RealisticJobPreview/日本語訳「現実的な仕事情報の事前開示」)は、アメリカで提唱された「企業の良い部分のみでなく、悪い部分も含めてありのままの姿を求職者に提示することで、入社前に企業の良い面・悪い面を把握してもらい、人材定着を図る」ことを目的とした取り組み。幼い頃から情報過多のネット社会に囲まれ、SNSと共に育ち「リアルな姿・リアルな声」が重視キーワードになっている現在の新卒学生(Z世代)と親和性の高い取り組みとも言えます。
RJP理論が生み出す4つの効果
RJP理論の効果
・ワクチン効果
法人のリアルな姿(ポジティブ・ネガティブの両面)を包み隠さず伝えることで入職後のミスマッチ・失望・ギャップを緩和させる効果。
・スクリーニング効果
ネガティブ情報も踏まえて求職者が自分に合う法人を選択でき、互いのマッチ度を高める効果。またネガティブ面も理解した上で自己選択するため、入職後も安定的に働ける可能性が高まる。
・コミットメント効果
ネガティブ情報を開示して“誠実さ”を伝え、愛着心を高める効果。愛着が生まれると「この組織に貢献したい」という熱意や帰属意識にも繋がりやすく、エンゲージメント向上にも繋げやすい。
・役割明確化効果
「あなたにどのような仕事をして欲しいか、何を期待しているか」を明確に伝えることで、求職者に「働き方のイメージ」を持ってもらいやすくする効果。入職意欲・職場満足度の向上にも繋がりやすい。
この4つの効果から、
「法人への信頼を醸成・促進できる」
「法人風土・カラー・保育観に合う人財と出会いやすくなる」
というメリットが生まれ、
「早期離職の防止・定着促進・エンゲージメント醸成」が期待できるとされています。
RJP理論の実践ポイント
RJP理論提唱者ジョン・ワナウス氏から「実践にあたってのガイドライン」も示されているので、以下の点も意識しながら、RJP理論を取り入れてみてはいかがでしょうか。
RJP理論実践のためのガイドライン
1.RJPの目的を求職者に説明し、誠実な情報提供を行う
2.提供する情報に見合ったメディアを使用し、信用できる情報のみを提供する
3.現役の社員がリアルな情報を提供する
4.組織の実態に合わせて開示する良い情報と悪い情報とのバランスを考慮する
5.これら情報開示を採用活動の早期段階で行う
※具体的な取り組み 一例※
・若手職員との対話の時間を設ける
・職員インタビューコンテンツ作成(紙/WEB/動画etc)
・インターンやボランティア、保育体験の実施
・SNSで職員のリアルな姿を発信
定着と育成の両輪で人材不足解消へ
実は、今回ご紹介したRJP理論、初めて提唱されたのは1970年代。
約半世紀に渡り、度々注目されてきた取り組みです。
採用だけでなく「どう早期離職を防ぎ、定着・育成に繋げるか」が、今も昔も重視されてきたことが窺い知れますね。
せっかく時間と手間とコストをかけ採用しても、早期離職になっては元の木阿弥。むしろマイナス…。
採用環境が厳しくなるほど、苦労して採用した職員に定着してもらい、法人を支える一員へ成長してもらうことが大切になってきます。
一方で「本当に採用が大変で、定着・育成への余力がない…」というお声もよくお伺いします。
RJP理論などの採用時の工夫はもちろん、
①職員1人ひとりの把握を強化し、フォロー体制を整える
②現場職員の負担削減施策を取り入れる
③職員が成長(成功体験)を実感できる仕組みを構築する
などなど…
今のうちから「入職後の定着・育成」も併せて力を入れていくのがおすすめです!
ぜひ、カタグルマにお声がけください。
最新のセミナー情報はこちら
執筆者プロフィール

八巻咲紀
株式会社カタグルマ カスタマーサクセス部









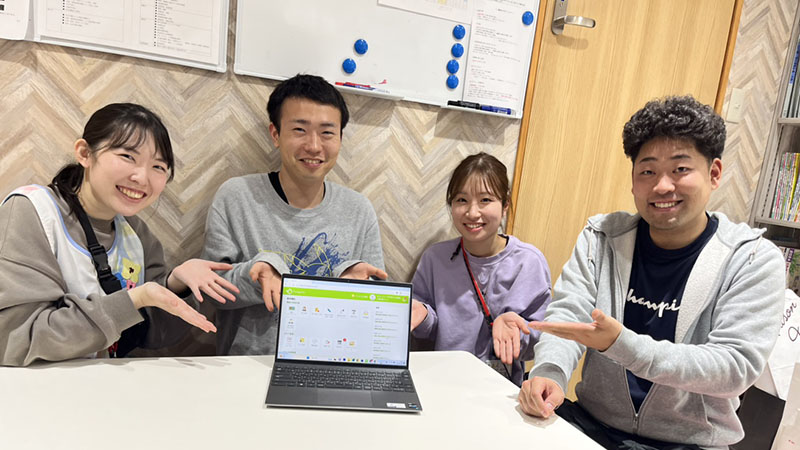
城南学戦様.jpg)





